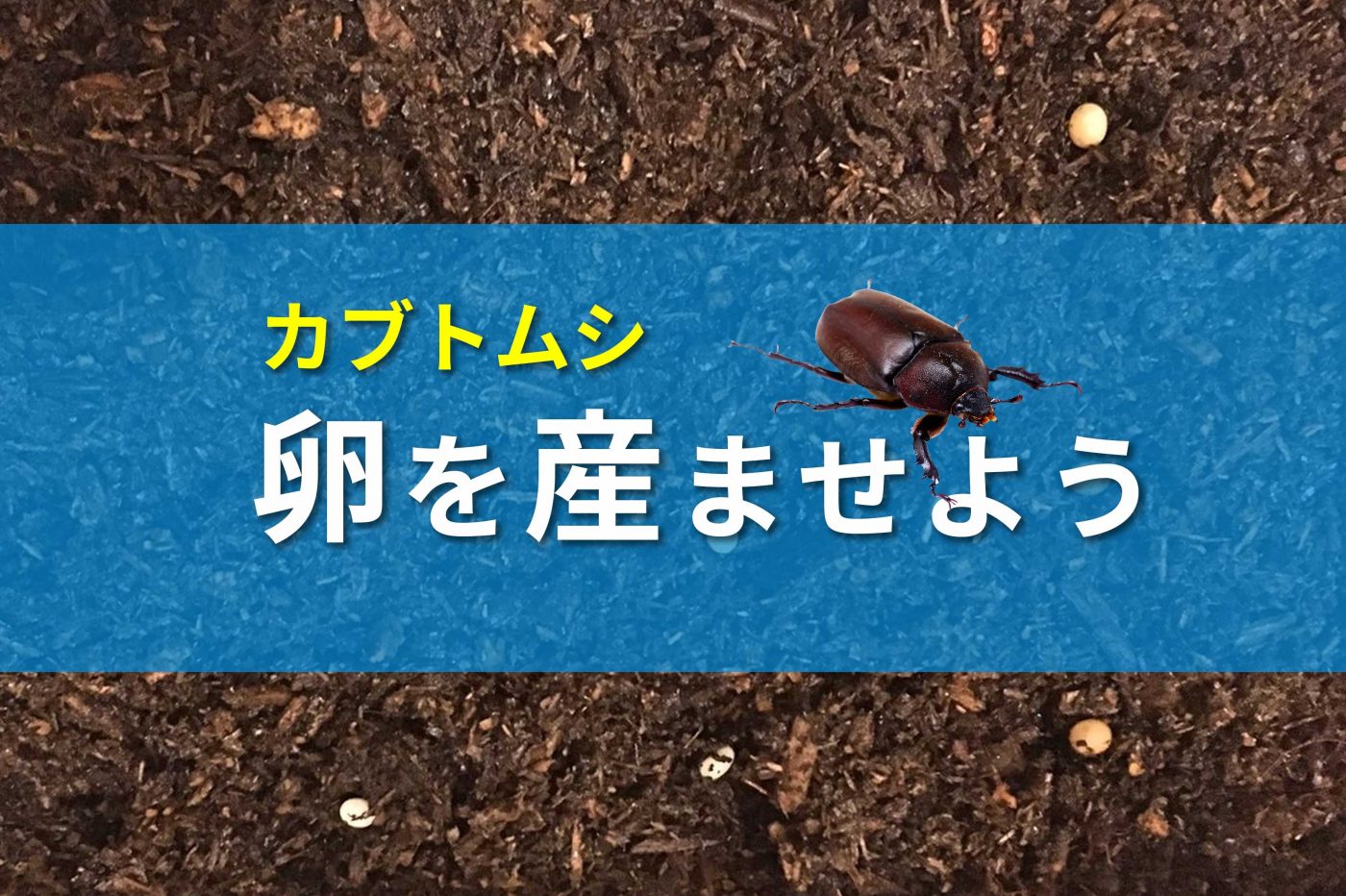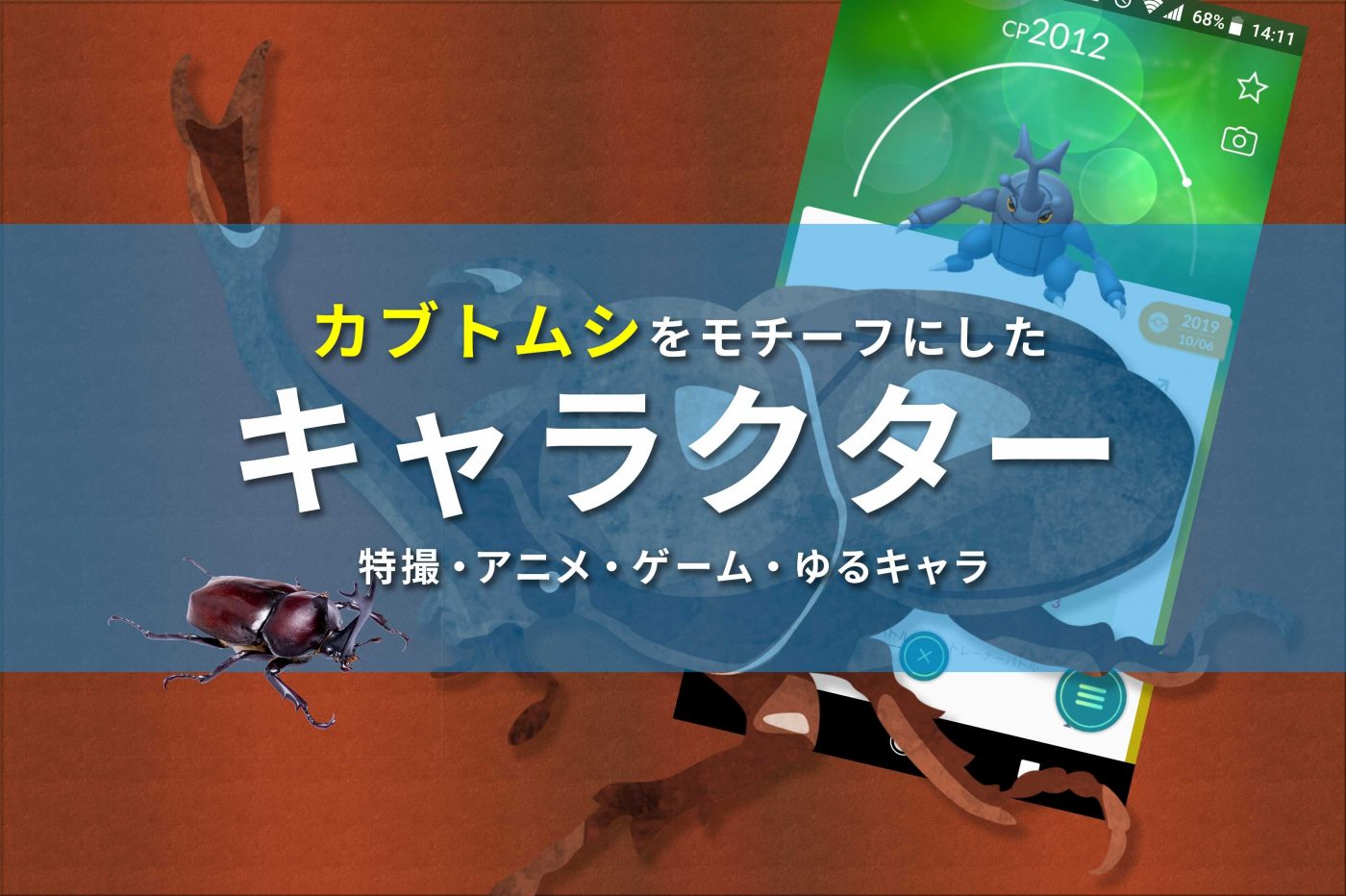カブトムシとは?
コウチュウ目に含まれるコガネムシ科のグループで、代表的な「カブトムシ」のオスには大きな角(ツノ)があり人気があります。その大きさから強さの象徴ともなっており、昔から鎧兜(よろいかぶと)のモチーフとして使われたりしてきました。
しかし、カブトムシの仲間にはオスでも「コカブト」や「クロマルカブト」のように、ツノが無いか目立たない種類もいます。
カブトムシを英語で「rhinoceros beetle(ライノセラスビートル)」
カブトムシは英語で「rhinoceros beetle(ライノセラスビートル)」と呼ばれます。一般的にはビートルだけでもカブトムシを指すことが多いですが、ビートルだけだとコウチュウの仲間全体を指す言葉なんですね。ですからクワガタムシもタマムシもみんなビートルです。
ライノセラスとは哺乳類の「犀(サイ)」のことで、サイのような角を持ったコウチュウの意味です。
しかし、みんなが知ってるカブトムシよりも、沖縄に生息するタイワンカブトのツノの方がまるでサイのようなんですね。別名もサイカブトです。
カブトムシの写真ギャラリー
Scarabaeidae
※クリックすると各ページに飛べます。写真と詳しい説明があります。

カブトムシの種類(亜種・日本・海外)
日本のカブトムシの仲間は数種類が知られており、一般的にはオスのツノが兜のように枝分かれしたカブトムシがしられています。
他にもサイのような一本角を持ったタイワンカブト(サイカブト)が南西諸島に生息しますし、コカブトは体長も2cm程度と小さく、オスでもツノがとても小さいですがカブトムシの仲間として知られています。
ツノのまったくない「クロマルカブト」はクロマルコガネとも呼ばれ、ツノがないので他のコガネムシと見分けもつきにくいです。
世界には約1,000種類のカブトムシが知られています。
カブトムシの生態/成長


卵・幼虫・蛹(サナギ)・成虫
カブトムシの仲間は完全変態をする昆虫で、幼虫のときと成虫の時の姿が大きく変わります。
卵から孵った幼虫は土の中で育ちます。そのまま土の中に蛹室(ようしつ)を作って蛹(サナギ)になり、成虫のカブトムシになると見た目も大きく変わり、地上に出て樹液などに集まります。
成長の速度はカブトムシによって異なり、日本のカブトムシの幼虫期間が数ヶ月であるのに対して、外国産のゾウカブトなどは幼虫期間が2~3年ほどもあります。
食べ物や餌(エサ)
カブトムシも種類によって食べるものは異なります。日本のカブトムシでは樹液に集まるものが一般的ですが、カブトムシの仲間の「コカブト」などはカブトムシの死骸やミミズなどを食べる肉食性です。
沖縄に生息する「タイワンカブト」はサトウキビなどの汁を吸っています。
海外のカブトムシも樹液や木の汁を吸うものが多いですが、ゴホンヅノカブトやタテヅノカブトなどは竹を傷つけて汁を吸います。

幼虫の冬の越し方
種類によっても異なりますが、日本のカブトムシは土の中で幼虫のまま越冬します。
カブトムシの寿命

日本のカブトムシは寿命はそんなに長くありません。成虫の寿命は野生で1~2ヶ月程度。
幼虫の時期から見ても、夏に産卵されて次の年の夏に成虫の寿命が尽きるので、カブトムシの寿命は幼虫の時期を含めても1年くらいです。
しかし、コカブトの仲間は半年~2年近く生きるものもいます。
世界のカブトムシを全体的に見ても、数年生きるものも多いクワガタムシなどと比べて、寿命はそんなに長くありません。
しかし、飼育下では丁寧に育てると2~3ヶ月程度頑張ってくれます。
これは、野生下だと危険が多いため長生きが難しいのです。野生の環境では天敵もいれば、同属とのメスをめぐる闘いで傷ついたりもします。
天候が悪いと体力も削られます。
そうすると、平均的に野生下では寿命は短くなるのです。
カブトムシの飼育方法や育て方

カブトムシの飼育は人気のジャンルです。国産、外国産、問わずに飼育している人も多く生き物の観察にはぴったりです。
意外に手間もかかりませんので子供の教育や自由研究にも向いている昆虫です。
日本のカブトムシを一度育てていれば、外国のカブトムシでも同じような方法で飼育できるものも多いです。
カブトムシの採集のコツや注意点
自然と触れ合うのに昆虫採集はもってこいです。しかし、せっかく出かけたらカブトムシを見つけたいですね!見つけるのにはコツもありますし、自然の中で楽しむには準備も必要です。服装などの注意点をまとめています。
カブトムシに関する、その他の記事
カブトムシにまつわる色んな話を紹介します。
タマムシやハンミョウなど他のコウチュウの仲間を見てみる
コウチュウ目(鞘翅目)まとめ 甲虫図鑑