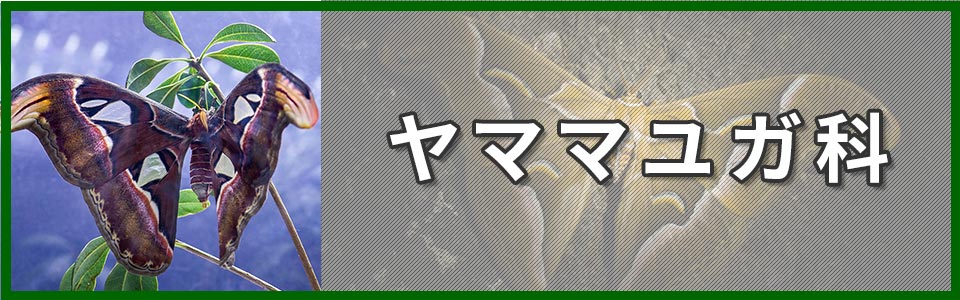写真ギャラリー
ヤママユってどんな蛾?
日本で見られる蛾の仲間の中でもかなりの大きさです。
灯火にもよく集る昆虫ですが、それでも見るたびに嬉しくなる昆虫ですね。
大きいし、ふわふわしているのでとても可愛いです。
一部地域では天蚕(てんさん)として、ヤママユを飼育することで天蚕糸(てんさんし)と呼ばれる高級繊維を利用していたりします。

天蚕(てんさん)と呼ばれるヤママユのシルク(絹)
日本では養蚕業として一部地域でヤママユが古くから飼育されてきました。
カイコを飼育した養蚕はよく知られたものですが、ヤママユを飼育して糸を取るというのは知らない人も多いのではないでしょうか?
ちなみに、カイコを利用したものを「家蚕(かさん)」、ヤママユを利用したものを「天蚕(てんさん)」と呼びます。(ヤママユ自体のことをテンサンと呼ぶこともあります。)
余談ですが、カイコやヤママユ以外にも糸を吐いて繭を作る昆虫はたくさんいます。それらのことを「野蚕(やさん)」とも呼んだりします。ワイルドシルクの名称で利用が進んでいたりもしますし、ヤママユの天蚕もワイルドシルクに含められて利用されたりもしています。
生産していた地域としては長野県が一番有名なようですが、他にも滋賀県や福井県で飼育されてきました。
ヤママユから取られた糸は天蚕糸(てんさんし)と呼ばれ、光沢の美しさや、伸度の高さ、丈夫さから高級繊維として重宝されています。
服だけでなく、日傘などにも利用されている番組を見たことがあるのですが、その中では天蚕糸を使った日傘は紫外線の吸収効果も高いことが紹介されていました。
しかし、カイコの飼育と違って、大量生産の難しさや手間がかかることがあまり見かけない理由ですね。
参考:ヤママユとカイコの繭


ヤママユの特徴
模様の特徴
4つの眼状紋とその大きな羽が特徴的です。
他の近い種類とも雰囲気は似ているのですが、クスサンなどとの違いは、4つの眼状紋や細く入った線状の模様で見分けられます。
一度見慣れたらわかるようになると思います。





色彩には変化がある
ヤママユの成虫は、その羽の色に変化があります。
黄色や赤褐色、暗褐色など色んなタイプがいます。


オスとメスの違い
前翅(ぜんし)を比較して見てみると、オスは細みで少し尖った印象。メスは幅広で丸みを持った印象です。
一番大きな違いは触角で、オスは羽毛状のふさふさした触角ですが、メスはクシ状の触角でふさふさしていません。




ヤママユの幼虫/イモムシ
大型のイモムシで、淡黄色の横線模様はお尻の方で褐色模様に繋がります。
よく見れば、少しきらめく白い銀紋も2つ並んでいます。


生態や習性など
成虫は餌(エサ)を食べない
成虫は口が退化し餌を食べることはありません。
幼虫の時に蓄えた栄養だけで活動をします。
ですから、羽化するとすぐに交尾をするためにメスを探さないといけません。
幼虫の糞(ふん)
花形の変わった形のフンをします。
排泄する部分の形状によるみたいですね。


夜行性で光に集まる習性がある
ヤママユは暗くなってから活動する夜行性の昆虫です。
光に集まる習性を持っているのでライトトラップなどでもよく見られます。
光に集まる習性のことを「走光性」と呼んでいます。
フェロモン
ヤママユはオスとメスが出会うためにフェロモンを利用します。
メスは腹端にフェロモン腺を持っていて、オスを誘います。
オスの触角がフサフサなのはこのフェロモンを感知する精度を高めるためと考えられています。
卵で越冬
ヤママユは卵の状態で冬を越します。
亜種(種類)
ヤママユは住む地域によっていくつかの亜種に分けられています。
日本では、本州を中心に見られる基本型のものと、奄美大島亜種、北海道亜種の3亜種が見られます。
| 学名 | 生息地 |
| ヤママユ(基亜種) Antheraea yamamai yamamai | 本州、四国、九州、対馬、屋久島 (ヨーロッパ) |
| 奄美大島亜種 Antheraea yamamai yoshimotoi | 奄美大島、沖縄島 |
| 北海道亜種 Antheraea yamamai ussuriensis | 北海道、中国北部、極東ロシア |
| Antheraea yamamai superba | 台湾 |
| Antheraea yamamai bergmani | 朝鮮半島 |
ヨーロッパで見られるものは、日本からの移入種のようです。
成長の様子
ヤママユを含む蛾の仲間は「完全変態」をする昆虫です。
完全変態とはサナギの期間があることで、幼虫時代と成虫とでは大きく姿が変わることが特徴的です。
ヤママユの幼虫は4~6月頃に発生し、成長した幼虫は葉を巻いて繭を作ります。
7~9月に羽化した成虫は、交尾・産卵をして、卵の状態で冬を越します。
年に一回だけ発生する昆虫です。
卵
灰色で、まだら模様の入った卵をある程度まとめて産卵します。


孵化(ふか)
硬そうな卵に見えますが、幼虫は穴を開けて出てきます。


幼虫
孵化(ふか)したばかりは黄色でトゲトゲした印象の毛虫型イモムシ。
餌を食べて大きくなってくると緑色に変わっていきます。
成長すると、透き通った緑色の綺麗なイモムシですが、とても大きく肉感に溢れています。
捕まる力も強いので、手に乗せるとちょっとびっくりします。
オオミズアオの幼虫などと印象が似ていますが、尾部の褐色斑があることや、頭部近くの棘の生え方などで見分けは出来ます。
ブナ科の植物の葉などを食べてすくすくと育っていきます。
一齢幼虫





二齢幼虫





三齢幼虫



四齢幼虫~終齢幼虫






繭(まゆ)と糸
木の枝や葉っぱにくっつくように繭を作ります。
黄緑から緑色の美しい繭で、冬の雑木林などでは空の繭がよく見つかります。
この繭を作る時に吐き出す糸は、天然のシルクとして利用することもあります。
その中でサナギになるのですが、大きさは35mm~45mm程です。
メスのほうが大きいサナギになります。
一ヶ月ちょっとで大きな成虫が羽化してきます。




蛹(サナギ)
繭が完成すると中で蛹になります。
少し中の様子を拝見させてもらいました。




成虫
大型のガでとても美しい模様を持ちます。

分布や生息環境
日本では北海道から沖縄の方まで全国的に見ることのできる昆虫です。
平地から山にまで生息しますが、山地に入ったときや、雑木林に入っていった時に見られることが多いです。
海外では台湾、朝鮮半島、中国、ロシア、スリランカ、インド、ヨーロッパと世界的に見ることができ、住む地域で5亜種に分類されています。
ヤママユの仲間をもっと見る!
ヤママユガ科まとめ 山繭蛾図鑑