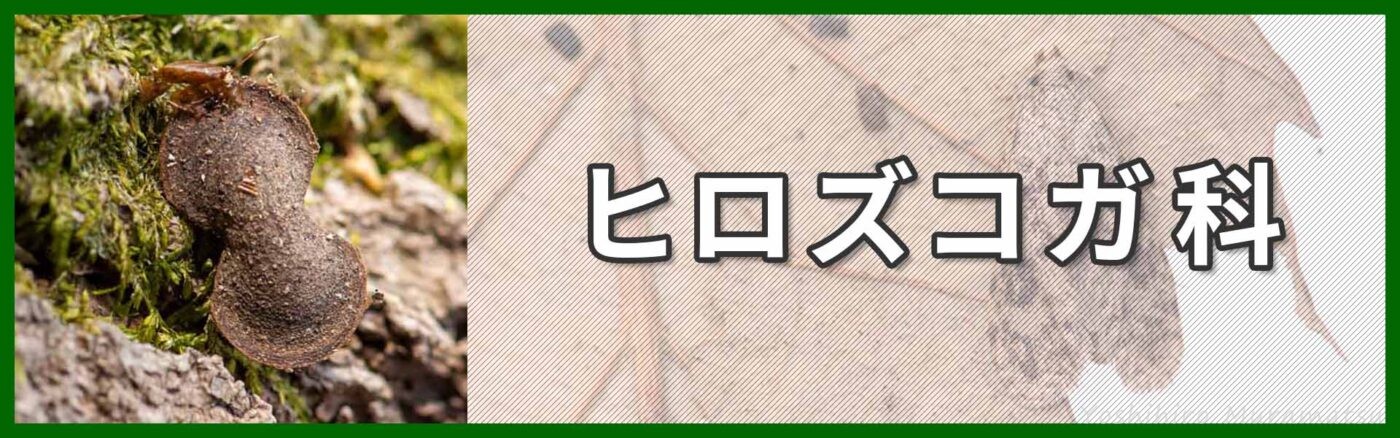写真ギャラリー
マダラマルハヒロズコガってどんな虫?
幼虫は平たく、鼓(つづみ)をイメージするような携帯巣(けいたいそう)を作って生活しており「ツヅミミノムシ」と呼ばれています。
(実際には丸を二個くっつけたような形)
ケアリたアミメアリなどの巣の中で、アリを捕食する変わった食性が知られていますが、巣の外で木にくっついているところなどもよく見かけます。
ヒロズコガ科
昆虫の分類でチョウ目に含まれる、一般的に「蛾(ガ)」と呼ばれる中の一群です。ヒロズコガ科の昆虫は、キノコや朽ち木を食べるものから、昆虫を捕食したり鳥の羽を食べたりする変わった食性のものがいることも知られています。
マダラマルハヒロズコガの特徴
携帯巣(けいたいそう)
携帯巣と呼ばれる平べったいミノを作って生活します。
材料は朽ち木の細片を使った「8」の字状のミノです。

幼虫
平たくなっていますが、上下のパーツが糸でくっついている構造のようで、キレイに二つにはずすことができました。
頭部は黒く、体は黄色の幼虫です。

そっとフタを閉じておいたら、また糸でつづってミノが復活していました。
生態の一部を紹介
食べ物や餌(エサ)
マダラマルハヒロズコガの幼虫は肉食性です。
ケアリはアミメアリの巣内から見つかることもあり、その中でアリを捕食しているようです。
他にも、死んだ昆虫やアリの食べ残しなども食べていると考えられています。
アリの巣周辺や、近くの樹木上や倒木や石の裏などでも見つかりますが、ミノが大きいので一度外に出たら中には入れないでしょうし、巣の中にいるやつはどうやって出てくるのでしょうね。

成長
幼虫



脱皮殻

成虫



分布や生息環境
本州から南西諸島まで見られます。
アリの巣の近くなどで見られます。
ヒロズコガの仲間をもっと見る!
ヒロズコガ科まとめ 広頭小蛾図鑑